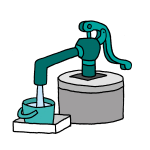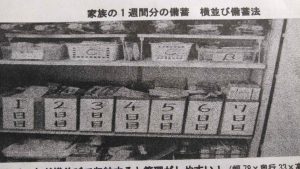平成22年度に始まった「いきいき体操」が、この度10周年を迎えました。
寝たきりや認知症を予防し、老後を豊かに暮らしたい。という想いから始まった「いきいき体操」。地域の皆さんが楽しく健康に過ごせるよう、活動してきました。
昨年のコロナ禍に於いては、緊急事態宣言解除後、密集を避ける為の2部編成、室内の十分な換気、除菌、又参加者の健康管理など、万全の感染対策をとり開催いたしました。
1月4日、本年最初の体操では10年前の立ち上げ当初から参加されている6名の方に表彰状と心ばかりの記念品を進呈いたしました。
一口に10年と言っても、継続するのは中々難しいものです。 コツコツと続ける事が健康の源なのだと、納得させてくれる元気な6名の皆さん。本当にお疲れさまです。ありがとうございます。また、引き続きコツコツ続けていきましょう!
そして、昨年一度も休まず通ってくれた皆さんには、先生方より表彰状と記念品が渡されました。コロナに負けず頑張ってくれて、ありがとうございます。
(詳しくは写真をクリック拡大してご覧ください!)
本年もコロナの状況を見ながらの体操になりそうですが、コロナに負けない体力づくりを、引き続き頑張っていきましょう!